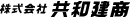もうすぐ春のお彼岸です。
「お彼岸」という言葉は、悟りを開いた極楽浄土の世界を意味する仏教用語です。
仏教用語というと宗教的な特別な印象を持ちますが、実は私達が日常的に
使っている単語にも仏教に関連した言葉がたくさんあります。
今月はそんな“意外な”仏教用語をご紹介したいと思います。
<仏教用語の一例>
『愛』『挨拶』『あばた』『有難い』『一期一会』『印』
『有頂天』『うろうろ』『縁起』『億劫』『看病』『冗談』
『上品』『大丈夫』『脱落』『旦那』『内証』『皮肉』
『不思議』『退屈』『独りぼっち』『知識』『利益』『無事』・・・
等々、馴染みのある言葉が多いですが、
この中から気になったものをピックアップしてみました。
『うろうろ』
「うろうろする」とよく言いますが、意味はあてもなく
あっちこっちに動き回ることです。
「うろうろ」を漢字で書くと「有漏有漏」となり、「漏」とは「煩悩」、
つまり「煩悩がある」という意味になります。
長い人生、人はあれこれと迷い、決断できずに苦しむこともあると思います。
そんな時でも自分の行くべき方向をしっかりと定め、うろうろせずに
進んでいくことが大切だということでしょう。
『看病』
病人に付き添って看病することですが、これも仏教からきた言葉です。
病人を看護することは仏教では重要な行いだったそうです。
ちなみにこの「看」という字は「手で触れて、目で見る」と書きます。
また、医療が発達していなかった頃の治療は、手を病人の患部に当てて
直していたそうです。
治療のことを「手当て」と言うように人の手には強いパワーが秘められて
いるのかもしれません。
仏教用語に限らず、語源を調べると言葉に込められている意味の深さに
気付かされます。
普段何気なく使っている言葉も、その意味を考えながら大切に使いたいものです。
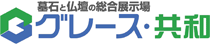
![[TEL:0120-48-2660]ホームページを見ましたとお電話ください!](https://www.kygp.com/grace/wp-content/themes/theme-mgcl/img/free-tel.gif)
![[メールでのお問い合わせ]24時間メール受付中](https://www.kygp.com/grace/wp-content/themes/theme-mgcl/img/btn-contact.gif)




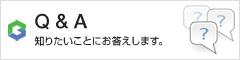
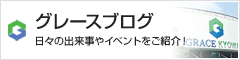




![お問い合わせ[TEL:0120-48-2660]](https://www.kygp.com/grace/wp-content/themes/theme-mgcl/img/bnr-contact.jpg)